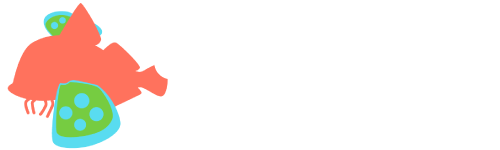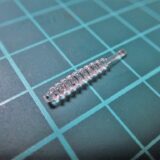こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。
さてさて、今回は渓流ルアー釣り講座をやっていきましょう。
今回は、私が実際に使っている渓流用おすすめミノー・選び方の基本を紹介していきます。
紹介するアイテムについては、ネット上でよく見られるような適当な寄せ集めや根拠の無いランキングではなく、公平な視点で実際に使い比べて魚を釣り、使いやすいものを選抜。
渓流用ミノー選びの参考にしてもらえたら嬉しく思います。
✔管理人の経験・実績
私の経験・実績としては
- 釣りのために仕事を辞めて移住、現在は魚釣りで生計を立てています
- 渓流釣りやタナゴ釣り~ヒラマサ釣りまで、色んな釣りができます
- 年間釣行数300以上(現在はほぼ365日釣行)
- メーカーからプロスタッフとしての勧誘あり
- メーカーの商品開発時に私のタックルインプレッションを活用
こんな感じでほぼ毎日釣行を重ねて釣りを中心に生活していて、実釣実績も残しています。
釣果実績については釣行記やTwitterを見てもらえれば、ほぼ毎日様々な魚を釣っていることが分かると思います(一番更新頻度が高いのはTwitter)。
渓流用ミノーの選び方
ミノーの種類
ミノーはリップ(くちびる・くちばしのようなもの)の形によって使い勝手が変わります。
ショートビル

リップが短く、引き抵抗が小さいミノー。
- アクションを与えても比較的潜りにくい
- トゥイッチングなど、ロッド操作に対してレスポンスが良い
このような特徴があります。
水量が少ない源流や小規模河川を中心に、渓流のミノーイングでは主力となるアイテムですね。
ミッドダイバー

ミッドダイバーは、ショートリップのミノーよりもやや大きく設計されたリップが特徴的です。
水深がやや深めなポイントを攻める時や、活性が低くて魚が川底に張り付いているような時に出番が来ます。
渓流用ミノーとしては、出番はやや少なくなります。
ディープダイバー

非常に大きなリップでしっかり水を掴み、強い波動で一気に深く潜行するのがディープダイバーと呼ばれるミノー。
渓流域では大きい滝つぼや淵狙いで使用することがありますが、全体的な出番は少なめ。
私の場合、深く潜るディープ系のミノーは1~2個ほど用意してあるだけで、使う場所は限られています。
リップレス

リップレスミノーは水を受けるリップが付いてない為、引き抵抗が小さいのが特徴です。
アクションはナチュラルにユラユラと柔らかく動きますが、渓流釣りではあまり使われません。
河川の上流を狙う渓流域のトラウトゲームでは、あえて購入する必要は無いでしょう。
 まるなか
まるなか
ミノーの重さ・比重
ミノーは重さ(比重)によっていくつかに分類ができ、流れの中を狙う渓流ルアーゲームにおいては非常に重要です。
- フローティング:水に浮くもの
- サスペンド:水とほぼ同じ比重
- シンキング:ゆっくりと水に沈む
- ヘビーシンキング・ファストシンキング:素早く沈む
比重の違いはこんな感じになりますが、よく使われるのはヘビーシンキングミノーやシンキングミノー。
比重が軽いミノーは流されやすく、渓流ルアーゲームでは水量が少ない河川や浅場狙いでの使用がメインになります。
近年の渓流ルアーゲームでは、特にヘビーシンキングミノーが良く使われていますね。
▼より詳しい解説は【渓流用ミノーの重さ・比重選びの基本徹底解説】を参考にどうぞ
ミノーのボディ形状
一般的な形

ボディがやや丸みを帯びており、小魚のような形状をしたミノーはベーシックに使える存在。
アピール力は平均的で、流れに対する強さとのバランスが良くてオールラウンドに使えます。
フラットサイド

ボディが偏平した形状をしているものは、フラットサイドミノーと呼ばれます。
ロッドアクションを与えた時のフラッシングが強く出せ、アピール力が高いです。
一方、極端なフラットサイドのミノーは使用感が少し独特で、好みが分かれます。
ボディの素材
樹脂
最近の量産型のミノーのほとんどは、樹脂素材で作られています。
強度が高くて品質が安定しているのが特徴で、価格も安価。
樹脂製の渓流用ミノーは1000円前後~1000円台後半くらいで購入できるものが大半です。
バルサ・ウッド
一方で2000円や3000円、場合によってはそれ以上の高価な渓流用ミノーも存在しています。
これらは、素材がバルサやその他のウッド素材で作られています。
樹脂素材と比較すると、比重が軽くて泳ぎ出しが早く、キレがありつつも柔らかなアクションをするのが特徴。
しかし、最近は技術の進化などにより、樹脂素材のミノーでも実釣には十分な性能があります。
ミノーの大きさ・サイズ

渓流域で20cm~30cm位までのヤマメやイワナなどを狙うのであれば、目安は5cm前後のミノーを選ぶのがおすすめです。
- 40mm前後:小さめ
- 45mm前後:やや小さめ
- 50mm前後:オールランド
こんな風に考えておくと分かりやすく、渓流域では45mm~50mmほどのミノーを使えば、だいたいなんとかなります。
▼より詳しい解説は【渓流用ミノーのサイズ・大きさ選び徹底解説】を参考にどうぞ
ミノーのカラー・色
ベースカラーで選ぶ

ミノーのカラー選びですが、簡単に選ぶならベースカラーで考えるとシンプルです。
- シルバー
- ゴールド
- パール
シンプルに選ぶなら、これらのカラーをベースにします。
ルアーのカラーは好みの部分も大きいですが、私の場合はシルバー系のカラーをメインに使っています。
視認性

渓流ルアーゲームで一番重要なのが、狙った場所にキャストすることとルアーの位置把握になります。
初心者の方は、まずは自分から見やすい色のルアーを選ぶのが絶対におすすめですね!
見やすさについては、背中のカラーを見て判断するようにしましょう。
例をあげると、
- チャート
- ピンク
- オレンジ
- ホワイト
このような目立つカラーが背中に入ったミノーを選んでおくと、非常に使い勝手が良いですよ!
 まるなか
まるなか
▼より詳しい解説は【渓流用ルアーカラー選びの基本徹底解説】を参考にどうぞ
渓流トラウトルアー初心者におすすめなミノー
まずは初心者の方や、どれを選んだらいいのか分からない方におすすめなものを、使い分けができるようにピックアップ。
各社数えきれないほどのルアーを購入して実際に使い比べ、その中から選抜しました。
ヘビーシンキング、シンキング、フローティング。
各種のミノーが揃えられます。
どれもベーシックで使いやすく、実績も十分。
これらを用意しておけば、極端なものを除いた大半の状況はカバーできます。
スミス Dコンタクト50

- 全長:50mm
- 重量:4.5g
- 比重:ヘビーシンキング
スミスのDコンタクト50は、ヘビーシンキングミノーの元祖にして王道。
源流域~小規模な本流までカバーでき、使いやすさ・実績ともに文句なしのトラウト用ミノーですね。
そこそこ流速のある場所を広くカバーでき、ロッドアクションを与えた時の平打ちダートが非常に良いミノー。
テンポよく釣り上がることもできますし、ラインテンションを掛けたドリフトで使うのも高実績。
ヘビーシンキングミノーを1つ選べと言われたら、まずDコンタクトを選びますね!
▼使用感の詳しい解説は【スミス Dコンタクト徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
スミス Dコンパクト45

- 全長:
- 重量:3.5g
- 比重:ヘビーシンキング
Dコンタクトの弟分的なミノーがDコンパクト40。
同じくヘビーシンキングミノーですが、少し水量が少ないポイントだったり、魚が小さめで50mmクラスのミノーだと食いが悪い状況などにおすすめ。
5mmの違いが実釣時にかなり大きく影響することがあり、Dコンタクトだと追ってくるのに食わず、Dコンパクトに変えた途端連発するような経験も多くしていますね!
▼使用感の詳しい解説は【スミス Dコンパクト徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
ジャクソン 奏 50

- 全長:50mm
- 重量:5g
- 比重:ヘビーシンキング
Dコンタクト・Dコンパクトと続き、3つめのヘビーシンキングがジャクソンの奏。
使い分けとしては、Dコンタクトでは少し泳層が浅く、もう少し深く潜らせたい場面におすすめです。
奏は程よく長いリップを採用しているんですが、引き抵抗が大きすぎず、ショートリップのミノーに近い感覚で使えるのが非常にありがたいんですね。
増水時や、ちょっとした滝つぼ・淵などを狙う時に効果を発揮しますよ!
▼使用感の詳しい解説は【ジャクソン 奏徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
ジャクソン メテオーラ52

- 全長:52mm
- 重量:5g
- 比重:ヘビーシンキング
ジャクソンのメテオーラは、奏よりもクイックなアクションとやや浮き上がりやすい特性を持っているヘビーシンキングミノーですね。
非常にハイレスポンスでヒラヒラ泳ぐので、ラインのコントロールやロッド操作が苦手な初心者の方でも、キッチリと泳がせやすい特徴がありますね!
あまり強い流れでは少し流されやすいので、平水時や少し規模が小さい河川を攻める時におすすめです。
▼使用感の詳しい解説は【ジャクソン メテオーラインプレッション】を参考にどうぞ。
タックルハウス バフェット S43

- 全長:43mm
- 重量:2.4g
- 比重:シンキング
タックルハウスのバフェットS43は、ショートリップのシンキングミノー。
これまでに紹介したヘビーシンキングミノーよりも比重が軽く、水量が少ない支流やチャラ瀬などを狙う時におすすめです。
キビキビ泳いで食わせ能力が高く、もう15年以上は使い続けているミノーですね。
渓流トラウトはもちろん、海のライトゲームでも実績超多数のお気に入りです。
▼使用感の詳しい解説は【タックルハウス バフェット徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
ダイワ ドクターミノーⅡ 50F

- 全長:50mm
- 重量:2.6g
- 比重:フローティング
ドクターミノーⅡ50Fは、水に浮くフローティング仕様。
非常にコスパが良く、初心者の方にも買いやすいのが嬉しいミノーです。
バフェットと同じく、水深が浅い場所を狙ったり、流れが緩い場所で効果を発揮します。
アクションはやや大きめでアピール力が高く、手元に伝わる操作感が分かりやすいミノーですね!
▼使用感の詳しい解説は【ダイワ ドクターミノーⅡ徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
渓流ルアーにおすすめなヘビーシンキングミノー
近年のベーシックな存在、沈むのが早いおすすめなヘビーシンキングミノーをいくつか紹介していきます。
※ヘビーシンキングミノーについてより詳しく知りたいという方は、【渓流用ヘビーシンキングミノーのおすすめ・使い分けのコツ解説】を参考にしてみてください。
バスデイ もののふ 35・45・50

- 全長:35mm、45mm、50mm
- 重量:3g、4g、4.6g
- 比重:ヘビーシンキング
バスデイから2022年に発売されたヘビーシンキングミノーがもののふ。
程よい体高と偏平したボディで、ヒラ打ちダートを発生させます。
ややリップが大きめで操作感も分かりやすく、ロッドアクションを与えると比較的しっかりとブレーキが掛かる味付け。
偏った癖が無く、オールラウンドに使いやすいミノーですね!
基本は45mmまたは50mmがおすすめですが、食い渋りやピンスポット狙いに35mmも良いですね!
▼使用感の詳しい解説は【バスデイ もののふ徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
スミス Dインサイト 44・53

- 全長:44mm、53mm
- 重量:4g、5g
- 比重:ヘビーシンキング
スミスのDインサイトは、極端なフラットサイドボディが特徴なヘビーシンキングミノーですね。
使用感はやや癖があるので、好き嫌いが分かれやすいミノーかもしれませんが、上手に使うとかなり強い武器になります。
小規模なフィールドなら44を。
里川など、ある程度開けていて水量があるフィールドなら53がおすすめです。
若干ラインスラッグを出した柔らかなトゥイッチで使うのがコツで、強くアクションさせると良い動きが出ません。
慣れてくると、滑らかさのあるヒラウチを出せるようになります。
フラットサイドながら非常に浮き上がりにくく、ドリフトで使ったりするのもかなり効果的ですね!
▼使用感の詳しい解説は【スミス Dインサイト徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
メジャークラフト ファインテールエデン 45S・50S

- 全長:45mm、50mm
- 重量:3.7g、4.5g
- 比重:ヘビーシンキング
メジャークラフトのエデンはフラットサイドのボディ形状+やや大きめのアクションでしっかり泳ぐのが特徴的なミノー。
メーカー的には「S」表記ですが、比重は一般的なヘビーシンキングミノーになっているので要注意!
ヘビーシンキングモデルは非常に高比重になり、かなり強い流れを攻めるためのミノーです。
渓流用ミノーとしては、アピール力が高めに設定されているので、小場所狙いというよりもやや開けた場所や水が濁った時におすすめ。
このミノーも偏った癖が無く、フックも比較的強いものが付いていてコスパ良好ながら使いやすいですよ!
▼使用感の詳しい解説は【メジャークラフト エデン徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
バスデイ ボトムトゥイッチャー 42ES・50ES

- 全長:42mm、50mm
- 重量:3.7g、5g
- 比重:ヘビーシンキング
ボトムトゥイッチャーはバスデイのヘビーシンキングミノー。
アクションの質がDコンタクトやエデンとは少し違いがあり、やや控えめで安定したスイミングを見せます。
主にただ巻きや、ただ巻きの中に時々ロッド操作を入れる使い方がおすすめですね。
Dコンタクトなどよりも浮き上がりにくい為、流れが強い場所でもボトム付近のレンジをキッチリとおしやすいのがボトムトゥイッチャーの良いところ!
ただ巻きやドリフトなど、流れに対して無駄にミノーを操作せずに使いたい時に活躍するはずです。
▼使用感の詳しい解説は【バスデイ ボトムトゥイッチャー徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
DUO スピアヘッドリュウキ 38S・45S・50S

- 全長:38mm、45mm、50mm
- 重量:2.8g、4g、4.5g
- 比重:ヘビーシンキング
スピアヘッドリュウキはフラットサイド気味のボディでアピール力が高く、ロッド操作を与えた時のヒラウチが良い感じ。
サイズの割に体高があってボリューム感がやや大きく、渓流では45Sをメインに使用しています。
アピール力が高いヒラウチアクションが効果的ですが、流れに対する粘り強さはDコンタクトやボトムトゥイッチャーなど、他のルアーに比べるとやや劣る印象があります。
非常にコスパが良く、釣具店で見かける機会が非常に多いミノーの1つですね!
▼使用感の詳しい解説は【DUO スピアヘッドリュウキ徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
DUO 新型スピアヘッドリュウキ46S・51S

- 全長:46mm、51mm
- 重量:5g、5.5g
- 比重:ヘビーシンキング
2022年に追加になった46mm、51mmの新型のリュウキ。
これまでのものよりも高比重化されていて、若干流れに弱かったデメリットが消されています。
一方でアクションはヒラヒラ感が控えめになり、パワーのあるウォブリングが強化。
投げやすさやレンジキープ能力はアップしていますが、食わせ能力としては旧モデルのリュウキの方がやや上ですね。
ですので、新型が一概に良いとは言えず、流れへの強さや食わせ能力などを総合的に判断し、自分に合ったものを選ぶのがおすすめ。
▼使用感の詳しい解説は【DUO 新型スピアヘッドリュウキ徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
メガバス グレートハンティングミノー フラットサイド 50FS

- 全長:50mm
- 重量:4g
- 比重:ヘビーシンキング
メガバスのグレートハンティングハンプバックフラットサイドのFS(ファストシンキング)モデルは、ヘビーシンキングミノーとしてはやや軽めの比重が大きな特徴。
この絶妙な軽さにより、シンキングミノーとヘビーシンキングミノーの間を埋める存在として使い勝手が良いですね!
アクションは、フラットサイドボディによるフラッシング+ワイドなスライドダート。
水平気味の姿勢でフォールするので、ヘビーシンキングミノーの中ではポーズやスローなアクションが使いやすく、食わせ能力の高さが光りますよ!
▼使用感の詳しい解説は【メガバス グレートハンティングフラットサイド徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
浅場狙いにおすすめなシンキングミノー
ここから先は、実際に私が色んなミノーを使ってみて、使いやすいと感じたおすすめアイテムを紹介していきましょう。
まずはゆっくり沈むシンキングミノーから。
ダイワ ドクターミノーⅡ 42S・50S

- 全長:42mm、50mm
- 重量:3g、3.5g
- 比重:シンキング
ドクターミノーも渓流用ミノーとして超定番の位置づけで、モデルチェンジしながらずっと残っているアイテムですね。
キレのあるダートアクションとフラッシングにより、アピール力が高めに設計されているミノー。
バフェットよりもややアクションのパワーが大きくて大雑把な感じはしますが、コスパに優れていて、初心者の方でも買いやすいですね。
慣れるまではキャストミスでルアーを岩にぶつけたり、木に引っ掛けたりすることもあるので、安くてしっかり使えるミノーを探している方にイチオシ!
オールラウンドに使うなら50S、小規模河川・ピンスポット狙いなら42Sがおすすめです。
▼使用感の詳しい解説は【ダイワ ドクターミノー2徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
ダイワ ドクターミノージョイント 42S・50S

- 全長:42mm、50mm
- 重量:1.8g、3.1g
- 比重:シンキング
ドクターミノージョイントはあまり見られないタイプのジョイントタイプのミノーですね。
ネチネチと狭いスポットを狙ったり、ドリフトで使うのが得意です。
ジョイント部が独特な「クネリ」を発生させ、ドリフトやスローなトゥイッチで柔らかなアクションを発生させます。
ヘッドを左右に動かしつつ、一点で誘い続けるのが得意なので、スレた魚をピンスポットから引っ張り出したい時などに活躍しますね!
一方で流れが速い場所をアップストリームで探るのは苦手なので、ジックリ釣りたい時に投入するのがおすすめです。
▼使用感の詳しい解説は【ダイワ ドクターミノージョイント徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
ダイワ シルバークリークミノー スローフォールカスタム

- 全長:40mm
- 重量:3g
- 比重:シンキング
ダイワのシルバークリークミノースローフォールカスタムですが、ドクターミノーシリーズよりもアピール力は控えめ。
食わせ能力を重視したミノーで、ラインテンションを掛けて使うとフォールスピードが一気に遅くなります。
チャラ瀬狙いや減水時・小規模な支流狙い等におすすめで、水深が浅い場所をキッチリ引けるのがメリットですね!
40mmのボディは食わせ能力が高く、食い渋りや小型が多い場面にも強いです。
▼使用感の詳しい解説は【ダイワ シルバークリークミノー スローフォールカスタム徹底インプレッション】を参考にどうぞ。
スカジットデザイン チップミノー 40SS

- 全長:40mm
- 重量:2g
- 比重:シンキング
少しマニアックなミノーになりますが、もともとバルサ素材のミノーだったチップミノー。
このミノーの良さは飛距離や大きなアクションではなく、立ち上がり抜群の反応速度と動きのキレですね。
弱い水流でもヒラヒラと舞うように動き、繊細な誘いで非常に効果を発揮します。
水深が浅い源流や支流を打って行く時に使いやすく、プラスチック素材になっても、一般的なミノーよりも優れたレスポンスの良さは健在。
高速トゥイッチで大きく水を動かして釣る使い方にはあまり向いていませんが、繊細に使うことで効果を発揮する、スローシンキングミノーですね!
渓流ルアーゲームにおすすめなフローティングミノー
ラストは出番がやや少なめですが、超浅い場所を狙ったり、浅場をドリフトさせたい時に活躍するフローティングミノー。
※フローティングミノーについてより詳しく知りたいという方は、【渓流用フローティングミノーのおすすめ・使い方徹底解説】を参考にどうぞ。
タックルハウス バフェットリリィ

- 全長:45mm
- 重量:3g
- 比重:フローティング
バフェットリリィは長めのリップが特徴的なフローティングダイバー。
アクションを与えると素早くレンジが入るので、一般的なショートリップのシンキングミノーよりも縦の動きが出しやすくなっています。
直接キャストするのが難しい、木が生い茂った場所の下の淵や岩陰を狙ったりするのが得意ですね!
重量も3gあり、フローティングの割には投げやすくなっています。
スミス Fセレクト 51

- 全長:51mm
- 重量:2.6g
- 比重:フローティング
スミスのFセレクトは、重心移動システム搭載のスローフローティングミノー。
明滅がしっかりと出るウォブンロールは軽快で、フローティングミノーらしいキレの良さがあります。
浮力が控えめで投げやすく、フローティングミノー特有の投げ難さが目立ちにくくなっているハイバランスなミノー。
ただ巻きやソフトなトゥイッチングにおすすめですね!
次に読みたいおすすめ記事!
▼【実釣比較】渓流トラウト用ヘビーシンキングミノーのおすすめ・使い分けのコツ解説
渓流ミノーイングのベーシック、ヘビーシンキングミノーを徹底比較解説。
▼【実釣比較】渓流におすすめなフローティングミノー・使い方徹底解説
浅場狙いに強い!フローティングミノーを徹底解説
渓流釣りはフックの消耗との戦いです。交換フックは必ず用意し、針先がベストな状態を保つのは超重要です!
渓流ルアー釣りに必要な基礎知識やタックル選びなど、知っておきたい基本をまるっと解説します。
全て管理人の実釣経験に基づいたコンテンツになっています。