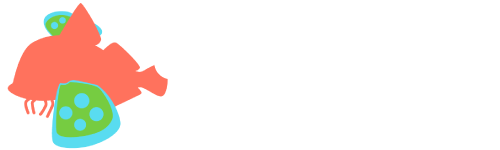こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。
さてさて、今回はショアジギング講座をやっていきましょう。
今日のテーマは、夏のショアジギングで釣れる魚や、攻略のためのコツを紹介していきます。
ショアジギングの本格シーズン到来となる夏場は、青物を中心に様々な魚が狙えます。
しかし、水温変化などによって釣れる場所が偏ったりすることもあります。
魚の行動パターンなどを知っておくと、釣果アップにつながるはずです。
※今回は「夏」のショアジギングについて絞った解説をしていきます。
1年の時期・シーズンの流れについては「ショアジギングの時期・シーズン解説」を参考にどうぞ。
✔管理人の経験・実績
なお、私の経験やショアジギングに関する実績としては
- 年間釣行数250~300以上
- メタルジグオンリーでサーフのヒラメ・マゴチを月間100枚以上・半年で300枚以上
- カンパチ狙いのショアジギングで2か月弱ボウズ無し
- 釣具店・メーカーにて私のタックルインプレや釣り方の活用あり
こんな感じで、基本的に毎日様々なジャンルの釣りをして生活していて、実績も残しています。
困った時の役に立ててもらえたら、嬉しく思います。
おすすめ動画
▼夏のショアジギングを動画で徹底解説
夏のショアジギングで釣れる魚・ターゲット

まずは夏のショアジギングで狙える魚について、代表的なものを紹介していきましょう。
ざっくりと簡単にまとめておくと、
- ブリ(主に幼魚)
- カンパチ(主に幼魚)
- ヒラマサ
- サバ
- ソウダガツオ
- シイラ
- アジ
- マダイ
- タチウオ
- マゴチ
- ハタ
地域によって生息する魚種に差はありますが、このような魚が狙いやすいことが多いですね。
青物:夏は数釣り中心
夏といえば青物釣りという印象がありますが、水温が高くなる夏場は、良型狙いというよりも数釣りが中心になる地域が多くなります。

私が住む静岡を例に挙げてみると、夏のショアジギング開幕当初は、サバやブリ・カンパチの幼魚などが釣れ始めるパターンが代表的。
その後さらに水温が上がってくると、シイラやソウダガツオが釣れ始めて盛夏を迎えるパターンですね。
また、小型の回遊魚であるアジは、梅雨時期前後に産卵期を迎えます。
基本的に岸から釣れるアジは小型が中心になりやすいですが、この産卵期となる初夏は潮通しが良い外向きの堤防やサーフ・磯などから、40cmを超える大型が狙える場所もあります。
アジといっても40cm前後になると、30g前後のメタルジグにもバイトしてくるので、ショアジギングのターゲットとして成立することも多いですね!
全体としてみれば、夏の時期のショアジギングは「だいたい1kg前後までの小型魚がメインになる地域が多い」と、覚えておきましょう。

なのでタックルもガチのショアジギング用を使うだけでなく、スーパーライトショアジギングやライトショアジギングでお手軽にターゲットと遊ぶのも私のおすすめですね!
上物系
夏のショアジギングでは、地域によってマダイやタチウオなどが狙えます。

マダイは春~初夏を中心に、乗っ込みといい、産卵を意識して浅い場所に良型が差してきます。
だいたい7月位までを中心に、ショアジギングで釣果が期待できる地域もありますね。
マダイの場合は水温が高くなると水深が深い場所に落ちることも多いので、梅雨明け以降の夏本番になると、岸から釣れにくくなるパターンが良く見られます。
一方でタチウオの場合は、回遊次第でいつでも狙うことができ、釣れ具合については、地域性や年による差が非常に大きいですね。
フラットフィッシュ・根魚

底物系のターゲットですが、夏場はマゴチやハタが中心になることが多いですね。
マゴチは春~初夏にかけて産卵期を迎えるため、地域によってはかなりの個体数が接岸することもあります。
マゴチはヒラメと比較すると、濃い群れを形成することも多いので、魚が集まっている場所を見つけると連続で釣れる事も多いです。
夏のショアジギングとしてもおすすめなターゲットになり、マゴチを狙う時は、底付近をスローな操作で叩いて探るようにします。
魚さえいれば食わせるのは難しい魚ではないので、難易度自体はそこまで高くないですね。
一方、ヒラメの場合は梅雨時期くらいまでは春のヒラメシーズンを引っ張ることが多く、6月~7月上旬くらいまでは狙えることが多いです。
しかし、梅雨が明けて本格的な夏が到来すると、良型を中心に深場へ移動する個体が目立ちますね。
なので、夏場でもヒラメは狙えなくはないですが、小型のソゲサイズが中心になりやすい傾向があります。
また、夏場の根魚はハタ系がベストシーズンを迎えます。

ハタはカサゴやソイと比較すると高水温を好むため、夏~秋にかけて接岸する地域が多い印象です。
釣れるハタの種類は地域によって差がありますが、かなり積極的にルアーを追うので、ショアジギングでも良いターゲットになります。
青物狙いの際のボウズ逃れとしてもおすすめで、ボトム付近を叩けば比較的イージーに釣れますね!
夏に適した釣り場・ポイント選び
水温が上昇していく夏場のショアジギングですが、水温変化とともにポイントを適切に選ぶことが非常に重要になります。
適水温と魚の行動パターン
魚には、魚種によって住みやすい水温というのが決まっています。

例えば、夏の初期となる6月と8月では水温には違いがあり、梅雨明け以降晴れた日が続くと水温がどんどん上昇していくのが一般的です。
夏場の代表的なターゲットである青物の場合であっても、水温が高ければ高いほどいいかというと、そういうわけではありません。
意外と勘違いしている方も多いんですが、青物狙いだからといって、水温が高いほど活性が上昇するわけではないんですよね。
この適水温よりも海水温が上昇してしまうと、魚は暑さを避けるために沖の深い場所に落ちてしまうことが多くなります。
特に大型の魚ほど水温変化には敏感なことも多いので、魚の釣れ方が変わったときは水温の変化をチェックしてみましょう。
高水温期は沖の地形を見る
特に近年は水温が異常に上昇することが多く、そうなるとショアジギングは意外と苦戦を強いられることもありますね。
水温が高くなりすぎてしまうと、小型の青物はそれなりに釣れ続けるものの、ある程度の大きさ以上の魚は、暑さを避ける行動に出ることが目立つようになります。
同じ釣り場に通い続けていて、水温が上がってきた途端に釣れる魚のサイズが下がったとしたら、その時は水温上昇で魚が動いたことを疑うと良いですね。
釣り場の水深チェックは当然のことながら、意外と見落としがちなのが沖合の水深です。
例えば、沖合500mの地点で水深が100mの釣り場と30mの釣り場では、沖合がガクンと深くなっている場所の方が、魚の避暑地に近い釣り場の可能性が高くなります。
そうなると、魚の避暑地に近い釣り場の方が朝夕マズメを中心に「餌を食いに浅い場所に差してくる魚がやってくる場所」になる確率が高く、夏場の釣果も出しやすい印象があります。
なので、夏場に釣果をより安定して出したい方は、海底図などをチェックし、釣り場の沖合の地形などに目を向けると新しい発見があるはずですよ!
 まるなか
まるなか
潮通し

水深とともにチェックしておきたいのが、潮通しになります。
春や秋と比較すると、夏場は高水温によって水質悪化が起こりやすいです。
特に潮通しが悪くてフレッシュな水が供給されない場所は、茶色く濁った潮になってしまうこともあります。
こういった水質が悪い場所には、当然魚の回遊も少なくなりやすいので、新鮮な水が供給される場所を優先的に選ぶのがおすすめですね。
一方で秋の場合は、水温低下による水質改善や、魚が住みやすい水温になることで、奥まった場所にまで青物が回遊してくる可能性が高くなります。
時期・水温によって魚の行動パターンが分かるようになってくると、釣果の安定度は一気に高くなるはずですよ!
夏に狙う釣り場の水深目安
あくまで参考程度になりますが、夏場のショアジギングで私が主に狙う釣り場の水深(フルキャストした地点の水深)の目安としては
- 梅雨明けくらいまでの時期:水深5m前後以上
- 梅雨明け以降の時期:最低でも水深10m前後、できれば15m以上
こんな感じで、高水温になるほど、水深が深い場所を中心にポイント選びをしています。
夏のショアジギングと時間帯セレクト
夏のショアジギングにおける時間帯選びについて、解説していきましょう。
朝マズメ

夏に限ったことではないですが、一日のうちで最もショアジギングの釣果が出しやすいのは「なんだかんだで朝マズメ」という印象があります。
特に夏場は朝マズメが一番水温が低い可能性が高いですし、人間的にも釣りをするのが楽な時間帯ですよね。
実際に私の釣果としても、他の時間帯の倍以上は良く釣れる感覚があります。
青物・タチウオなどの回遊魚・底物問わず、朝マズメは魚の活性が高く、最もおすすめな時間になります。
日中
日中は非常に暑くて釣りが大変な時間になりますが、魚の活性はベイトフィッシュや潮の効き次第といったところ。

マズメの時間帯と比較すると釣果は劣りやすいですが、シイラやハタなどは、ある程度日が昇っている時間の方が釣りやすく、デイゲームでも十分に遊べます。
夕マズメ

夕マズメも朝マズメと並んでチャンスタイムとされますが、夏場のショアジギングでは、日中+α程度のチャンスにしか考えていません。
日によっては全く魚の活性が上がらないこともありますし、裏切られる確率が比較的高いのが夕マズメなイメージ。
一方で秋~冬にかけては、夕暮れの一瞬に良型の魚の時合いが来ることも多いので、時期によっては夕マズメを好んで釣行することもありますね。
夜間
夜間のショアジギングでは、主にタチウオなどを狙うことになりますが、ベイトの回遊次第ではブリやサバは夜間でも意外と釣れます。
ただし、夜は魚の動きがスローになるので、マズメの時間などに多用するようなハイピッチのジャークでは魚が付いてこないことも多いです。
ナイトゲームのショアジギングでは、スローなジャークとフォールを組み合わせたり、タチウオを狙う時はワームなどをうまく使うのがおすすめですね!
夏のショアジギングに使うタックルバランス
夏のショアジギングでは、地域によって釣れる魚の大きさにバラツキがあります。
適切なタックルを選ぶことで、より快適に・楽しく魚と遊ぶことができるはずです。
ライトショアジギング:高い汎用性

だいたい30cm後半~50cm前後までのターゲットを基準に、30g~40g程度のメタルジグを使うのがライトショアジギングと呼ばれる釣り方。
夏のショアジギングでは堤防やサーフなどを中心に、お手軽に使えて汎用性は非常に高いです。
離島などの大型魚狙いがメインになる場所以外では、夏のショアジギングでは一番使い勝手が良いでしょう。
タックルバランスの例を挙げておくと
- ロッド:シーバスロッドM~MHクラス。またはライトショアジギングロッド
- リール:4000番~5000番クラス
- PEライン:1.2号前後(1号~1.5号)200m以上
- ショックリーダー:20LB~30LB
- メタルジグ:30g~40gをメインに、重たくても50g程度
このようなタックルバランスが基準になります。
▼ライトショアジギングは汎用性が高く、中型魚をお手軽に色々狙えます。
詳しい解説については【ライトショアジギング初心者講座】を参考にどうぞ。
スーパーライトショアジギング:小型魚と手軽に・楽しく遊ぶ

ここ最近で流行り始めているのが、繊細なタックルを使って軽量ジグを扱うスーパーライトショアジギングですね。
主に30cm前後~大きくても40cm程度までの魚をお手軽に狙うのにおすすめで、ライトで良く曲がるロッドを使用するので、小さなターゲットでも引きが楽しめます。
タックルバランスの例を挙げておくと、
- ロッド:専用ロッド・エギングロッド・シーバスロッドLクラスなど
- リール:3000番クラス
- PEライン:0.8号200m(0.6号~0.8号前後)
- ショックリーダー:2.5号ほどを基準に、2号~3号前後
- メタルジグ:15g~20g程度
こんな感じになります。
スーパーライトショアジギングは、身近なフィールドでも楽しみやすく、ルアー釣り初心者の方にも非常におすすめですね!
▼スーパーライトショアジギングの詳しい解説は【スーパーライトショアジギング初心者・基礎徹底講座】を参考にどうぞ。
必要な基礎知識全般を解説します。
ショアジギング:良型狙いにおすすめ

ターゲットのサイズが2kg以上だったり、磯などの足場が悪いフィールドで釣りをする時は、パワーのあるショアジギングタックルを選ぶと良いですね。
使用するメタルジグは60g以上になり、狙うターゲットや釣り場の状況によって、タックルバランスは大きく変わります。
ヒラマサやシイラなどを狙う時や、離島などの大型魚が出やすいフィールドでは、メインタックルになる。
合わせて読むのにおすすめな関連記事!
▼夏のショアジギングを動画で徹底解説
▼ショアジギングの時期・シーズンを解説!
 ショアジギングの時期・シーズンの流れを基礎から解説。季節ごとに知っておきたい知識とは?
ショアジギングの時期・シーズンの流れを基礎から解説。季節ごとに知っておきたい知識とは?
▼ライトショアジギング初心者講座
▼スーパーライトショアジギング初心者講座