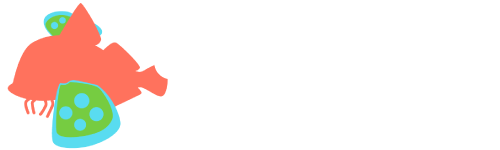こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。
さてさて、今回はライトワインド・マイクロワインド講座をやっていきましょう。
今日のテーマは、ライトワインド・マイクロワインドで釣れる魚について、代表的なものを紹介します。
これから挑戦する時のイメージ作りの参考にしてもらえたら嬉しく思います。
✔管理人の経験・実績
なお、私の経験やライトゲームに関する実績としては
- 年間釣行数250~300以上
- 専用タックルが発売される前からアジングやメバリングなどのライトゲームの経験あり
- カマス狙いのライトゲームで5か月間ほど連続でボウズ無し
- メーカーからプロスタッフとしての勧誘経験あり
- 釣具店・メーカーにて私のタックルインプレや釣り方の活用あり
こんな感じで、基本的に毎日様々なジャンルの釣りをして生活していて、実績も残しています。
 まるなか
まるなか
ライトワインド・マイクロワインドで釣れる魚の基礎知識
まずはライトワインドで釣れる魚・ターゲットについての基本となる知識から紹介していきましょう。
回遊魚・上物・底物。五目釣りができる
ライトワインド釣法は小型のワーム+ジグヘッドを使用する「ライトゲーム」と呼ばれる釣り方になります。

基本的には特定のターゲットを狙うというよりも、小型の肉食魚・雑食魚を何でも狙うことができます。
分かりやすく分類すると、
- 青物・回遊魚
- 上物
- 底物(根魚・フラットフィッシュなど)
このような3種類に分類することができます。
狙うターゲットによってアクションの速度を変えたり、ワームを泳がせるレンジ(泳層)を調整することで色んな魚を狙うことが可能になりますね。
ライトワインドのタックルバランス・ルアーのボリュームを考えると、だいたい20cm~30cm位の大きさの魚を狙うのに適しています。
時期によって釣れる魚は大きく変わる
ライトワインドに限らず、釣行する時期・シーズンによって釣れる魚は大きく影響を受けます。

例えば、青物や回遊魚を狙うのであれば、最も無難なのは「夏~秋頃」になる地域が多いですね。
一方で底物を狙う時は水温が下がる冬場の方が釣れやすいこともあり、時期によって釣りやすい魚種は変化します。
釣行するタイミングによってジグヘッドの重さを変えてみたり、狙うポイントをしっかり選ぶことが重要にです。
ライトワインドで釣れる青物・回遊魚
ここからは実際にライトワインド釣法で釣れる代表的なターゲットを紹介していきましょう。
まずは青物・回遊魚系から。
アジ
アジはライトゲームの代表的なターゲットで、ライトワインド釣法でも釣ることができます。

釣れるサイズは20cm前後になることが多いですが、釣れる時期は地域によってかなり差があります。
基本的にはm夏場を中心にサイズが小さく、秋~春先は釣れるサイズが大きくなる場所が多いでしょうか。
私の住む静岡の場合は、ルアーで狙えるサイズのアジが釣れるのは冬~春頃になるパターンが多いですが、一年中釣れる地域も多くあります。
カマス
主に港湾部の堤防を中心に回遊することが多いカマス。

カマスはかなり獰猛な魚でまとまった群れを作りやすく、ライトワインドでも好ターゲットになります。
釣れるシーズンとしては主に秋を中心に、夏~冬がメインですね。
地域によっては、大型のカマスが春先まで釣れる事もあります。
釣れるサイズはだいたい30cm~40cm前後になることが多く、アジなどを狙う時よりも少し強めのタックルを使った方が効率よく釣れることが多いです。
メッキ
メッキは小型の回遊魚の代表格で、速い動き・イレギュラーなルアーアクションに対する反応が非常に良いターゲット。

ライトワインドで狙うには非常に楽しい魚で、特に魚が少し深い場所に沈んだ時などに強い効果を発揮しやすいです。
主に秋頃に釣れる魚で、8月~11月位までを中心に12月位までがシーズンになる地域が多いです。
冬でも水温が下がりにくい地域の場合は、真冬でも釣れる可能性があります。
ワカシ・ツバス
ワカシ・ツバスはブリの幼魚で、だいたい40cm程度までの個体を指します。

どちらかといえばライトワインドで狙うよりも、メタルジグを狙ったショアジギングで狙いやすいターゲットです。
ワカシ・ツバスはメッキやカマスを狙ったりしていると外道で釣れる事もありますが、小型の餌を偏食している場面ではライトワインドが型にハマったりします。
状況によってはジグに食ってこない個体を食わせることができたり、青物なのでヒットすると楽しい引きが味わえます。
主に夏~初秋を中心に釣れる可能性が高い魚ですね!
カンパチ
カンパチもワカシ・ツバスと同様に夏~初秋を中心に狙えるターゲットになります。

カンパチは青物の中でも海底付近の根や駆け上がりなどに着く習性が強いです。
ですので、海底付近をライトワインドで探っていると釣れる可能性が高くなる傾向があります。
ヒットするとかなり強烈な引きを見せるので、タックルにはPEラインを使った強度のあるものを使用したいですね。
主に20cm後半~35cm位までがライトワインド・マイクロワインドで釣りやすいサイズです。
タチウオ
タチウオは港湾部や水深がある程度深いサーフで釣れる事が多いターゲット。

岸から釣りやすいのは、主に朝・夕マズメと夜間になります。
ライトワインドで狙う場合はメインターゲットとしてではなく、外道で釣れる事が多いですね。
小型のルアーを使用するとラインを切られる可能性が高く、ライトワインドよりも「普通のワインド」で狙うのがおすすめです。
時期・シーズンはかなり地域性が高いですが、基本的には夏~秋にかけて釣れる事が多いです。
タチウオの回遊量は地域性がかなり大きいので、釣れる場所と釣れない場所が比較的はっきりしています。
ライトワインドで釣れる上物
次は青物・回遊魚以外の主なターゲットを紹介していきましょう。
シーバス(セイゴ・フッコサイズメイン)

ライトワインドのダートアクションは、捕食スイッチが入っていないシーバス狙いにも効果があります。
特に、船の影や岸壁沿いなどに潜んでいる個体の捕食スイッチを入れるのが得意です。
釣れるサイズは主に30cm前後~40cm程度までのセイゴ・フッコサイズがメインですが、時々大きなスズキサイズがヒットすることもあります。
セイゴ・フッコは1年中狙いやすいターゲットですが、特に春・秋が狙い目ですね!
チヌ・キビレ
主に河川の河口部や水深が浅いポイントでライトワインドをしていると、チヌ(クロダイやキビレ)が釣れる事があります。

根回りやカキ殻など、海底がゴツゴツとしている場所で釣れやすい魚です。
大型を狙うなら春の乗っ込みクロダイを狙い、数釣りなら夏~秋がおすすめ。
水深が深い場所にいるチヌ・キビレはルアーへの反応が悪いことも多く、どちらかといえば水深が浅いシャローエリアを狙うのが効果的です。
ライトワインドで釣れる底物(根魚・フラットフィッシュ)
カサゴ・ソイ
カサゴやソイは根魚の代表格で、海底に根があるポイントで釣れる可能性が高いです。

シーズン的には冬場のターゲットになることが多いですが、実際は一年中狙えます。
カサゴの方がより海底付近にジッとしていることが多く、海底ギリギリをダートアクションさせて狙う必要があります。
ハタ
ハタはカサゴやソイよりも遊泳力が高く、餌を見つけると中層付近まで追ってくることも多いアグレッシブな根魚。

非常に引きは強く、注意しないと根に潜られることがあるので要注意。
基本的にライトワインドで狙えるのは、20cm~30cm位までの小型のハタがメインですね。
地域によって釣れるハタは種類が違いますが、オオモンハタ・マハタ・アオハタ・キジハタ・アカハタ・ヤミハタなどがメジャーです。
釣れやすい時期は夏場~秋にかけてで、水温が低くなると沖の深場に落ちることが多いです。
潮通しが良い地域や険しい根がある場所では、小型のクエ(モロコ)などが釣れることもあります。
メバル
メバルはライトゲームの代表的なターゲットで、ライトワインドでも狙うことができます。

基本的には水温が暖かすぎる場所には生息数が少なく、魚影の濃さは地域差がかなり大きいです。
時期としてはだいたい晩秋~春にかけて狙いやすく、ターゲットが少ない冬~春先の貴重な釣り物。
メバルはどちらかといえばただ巻き系の釣りがベーシックになり、ダート系の釣りはデイゲームや捕食スイッチが入っていない個体を狙う時に出番が多いですね。
フエダイ・フエフキダイ

フエダイは暖かい海にすむ魚で、西日本や暖かい地域を中心に釣れやすい魚です。
種類は多く、地域によって釣れる種類は細かな違いがある。
私の出身である静岡の場合は主に夏~秋を中心に狙いやすく、水温が高い時期に港湾部や河川の河口部の根回りを探ると釣れることが多いですね。
ハタと並んで非常に引きが強く、ヒットすると根に突っ込む性質があります。
場所によっては岸壁沿いに隠れているのが見えたり、サイトフィッシングで釣れる事もありますね。
釣れるサイズは20cm前後の小型が多いですが、九州や四国の場合はもっと大きいサイズが狙えるはずです。
ヒラメ

ヒラメはライトワインドで狙うメインターゲットというより、海底を叩いていると外道で釣れる事が多いです。
ライトワインドの場合は20cm~30cmクラスのソゲサイズが釣れやすいですが、運が良ければ大型も狙えます。
ヒラメ釣りのシーズンは春と秋がベストといわれますが、小型の個体は真夏でも比較的釣れやすい傾向があります。
港湾部やサーフの砂地や所々に根が入った場所を狙うのがおすすめ。
マゴチ
マゴチはヒラメと並んでフラットフィッシュの代表格。

こちらもライトワインドのターゲットとしては、他の魚を狙っている時の外道で釣れる機会が多いです。
シーズンは春~夏場を中心に釣れやすいですが、地域によっては一年中釣れます。
比較的水深が浅い場所で釣れる事が多く、港湾部やサーフ・河川の下流部でライトワインドをやっているとゲストで登場することが多いですね。
ライトワインドとワインドさせない釣り方の使い分け【メリット・デメリット】
ライトワインドはワームをダートさせて釣ることになりますが、同じターゲットを狙う場合であってもメリットとデメリットがあるので要注意。
回遊性が高い個体・食い気が無い個体に効果大
ワームに限らず、ルアーをダートさせることは魚の捕食スイッチをオフの状態から強制的にオンにする効果が期待できます。

ライトワインドは釣りのテンポが比較的速いので、効率よく広い範囲を探るのも得意ですね。
特に限られた短い時間に回遊してくる魚を効率良く釣ったり、活性が低くて普通にワームをただ巻きしても食ってこない状況では強い武器になりやすいです。

また、カサゴやハタなどの根魚は「そこに魚が居さえすれば」比較的簡単に釣れるターゲット。
こういう魚種を狙う時も、手っ取り早く広範囲をチェックできるワインド釣法は便利ですね。
魚をスレさせるのが早くなる可能性
一方でライトワインドのデメリットとしては、ワームが激しく動くことによって魚の違和感を感じたり、スレ(ルアーを見切ること)安くなることです。

回遊魚であるアジやカマスを狙う場合を例に挙げてみましょう。
これらの魚は回遊魚ですが、状況によっては回遊せずに一定の場所に居つく習性も持っています。
例えば、
- 回遊性が高い個体を狙う
- マズメなどの短時間しか魚が釣れない
- ただ巻きの釣りでは魚が反応しない
このような時は、ライトワインドをメインに使うのが効果的になることも多いです。
一方で
- 魚が釣れる場所が狭いスポットに限られる
- 回遊性が低く、同じ場所で魚が釣れ続ける(常夜灯周りの夜釣りなど)
こういう時に下手にライトワインドを使うと、魚がスレてしまって釣果が伸びなくなることがあります。
狭い限られたスポットから魚を抜いていくときは、ワームを使用する場合であっても「ただ巻きやリフトフォール」の釣りの方が良いことも多いですね。
同じターゲットを狙う場合であっても、状況次第でワインド釣法とワインドさせない釣り方をうまく使い分けるようにしましょう。
基本の考え方としては、ルアーを激しく動かしても・動かさなくても釣れる時は「できるだけ無駄に動かさないで釣る」方がおすすめです。
 まるなか
まるなか
まとめ!
今回はライトワインドで釣れる魚について、代表的なものを中心に紹介しました。

狙い方次第で色んな魚種を狙うことができるので、釣り方を工夫すればオールシーズンライトワインドは楽しめます。
ライトワインドはハマると強い効果を発揮しますが、状況によってダートさせないただ巻き系の釣りと使い分けることで、より釣果が伸びるはずです。
ライトゲームの釣り方の1つとして、効果的に使えるようになりましょう!
▼ライトワインドに使うロッドやリール・ワームなどのタックル選びの基本や基礎知識を知りたい方は【ライトワインド初心者講座】を参考にしてみて下さい。
全て管理人の実釣経験をもとに、実釣から選んだおすすめアイテムや基礎基本を解説します。