
こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。
さてさて、今回は少し魚についてお勉強をしていきましょう。
今日のテーマは「ブリとヒラマサの違い・見分け」についてですね。
これまで私は魚屋で毎日魚を捌いてきた経験があり、近海物の担当をしてきました。
ブリやヒラマサもかなりの数を見てきており、その経験を基に基本的な違いを紹介していきます。
おはようございます😃
今日はブリ12キロ、ヒラマサ7キロの共演です🐟
似ているようで形や身質は全く違いますね!さて、今日も頑張ります! pic.twitter.com/D3iCUMEfGa
— まるなか (@marunakafish) December 26, 2020
釣りが好きな方は、釣れた魚がブリ(幼魚含む)なのかヒラマサなのか気になることもあるはずです。
比較画像を沢山使い、できるだけ分かりやすく、詳しく解説します。
ここで見分けの基本を覚え、今後の役に立ててくださいね。
ブリとヒラマサの違い・見分ける時のチェックポイント
まずは目の前にある魚がブリなのかヒラマサなのか、違いを知る時に見ておきたいポイントをざっくりとまとめてみよう。
主な違い・チェックポイントとしては
- 旬の違い
- 体の形
- 口の形
- 顔つき
- ヒレの位置
- 腹びれ
- 尾びれ
- 大きさ
- 身質(味・食感)
- 生息場所・習性
ブリ・ヒラマサはこのような点において違いがあります。
総合的に見て見分けるべし!
ブリとヒラマサはパッと見ではかなり似ている魚です。
職業上毎日魚を見ている人間であれば、実物をパッと見れば魚種はすぐにわかるようになってくるもの。
しかし、個体によっては結構微妙なものも存在していますね。
なので、魚種を判断する時は体の一部分だけを見て行うと間違えが発生しやすく、魚体全体をチェックすることで判別の精度は上がります。
画像での判断は意外と難しい
釣果写真などでブリとヒラマサを見分けてほしいといわれることがありますが、実はこれは結構難しかったりしますね。

画像では実物と違って確認できる角度が一定になってしまい、これが意外と厄介です。
複数の角度からの画像があれば良いんですが、1枚だけの写真や同じようなアングルからだけだど結構微妙なこともあります。
写真の場合は、遠近感や撮影角度によって実物とは若干違ったように見えることも多く、ややこしい個体の場合は特に判別が難しくなりやすいですね。
旬の違い
ブリとヒラマサは旬に違いがあります。
ブリは秋~春先が旬!
ブリの旬ですが、実は地域によってかなり違いがあります。
基本としては冬~春先が美味しい時期ですが、少し細かく紹介しましょう。
基本的な流れとしては、北海道から旬が始まり、山形・富山・京都などの日本海側へ続きます。
その後九州・四国・三重などの東シナ海・太平洋側へと変化していきます。
各地域の旬の目安としては
- 北海道:9月~10月くらい
- 富山などの日本海側:11月下旬~2月・3月上旬くらい
- 九州:12月~3月くらい
- 四国・東海:3月~4月くらい
私の経験的にはこんな感じで、北海道と四国・東海地方の太平洋側ではかなり大きな差がありますね。

これは12月のブリ。
どちらも12kgクラスの良型、非常によく肥えている典型的な旬のブリですね!
特に最近は北海道の天然ブリが注目されるようになってきていて、毎年秋の早い時期に12kg・13kgなどの大型が入ってきます。
ヒラマサの旬は春~夏
ブリは水温が低い冬~春先にかけてが中心になりますが、ヒラマサの場合はブリの季節が終わったくらいからが旬といわれます。
ブリほどはっきりした旬は無いような気もしますが、だいたい4月・5月位から始まって7月・8月位までが目安ですね。
ブリとヒラマサの体形の違い
次は、ブリとヒラマサの体の形の違いについて見ていきましょう。
体の丸み・偏平度
ブリとヒラマサですが、ざっくり言うとの丸み・偏平の仕方に違いがあります。
- ブリ:体に厚みがあり、ラグビーボールのように丸っこい
- ヒラマサ:体が比較的薄くて平たい
超簡単に見分けるならこんな感じになります。
実際に両者を見てみると、

これは程よく肥えた寒ブリです。
10キロ以上ある長さ的にはメーターオーバーの個体ですが、ふっくらしているのが分かりますかね。

更に大きい15キロなどのコンディションが良い大型のブリになると、こんな感じで体がはち切れそうなくらい肥えてきます。
一方でヒラマサを見てみると・・・・

個体差は当然ありますが、ブリと比較すると丸々と肥えた状態にはなりにくく、少し平べったいです。
このような感じで、ブリとヒラマサは体の形に違いがあります。
同じ長さならブリの方が重たい傾向
標準的な体系のブリとヒラマサを比較した場合、同じ長さの場合は体に厚みのあるブリの方が重たいことが多いです。

上の個体がブリで、下がヒラマサ。
画像からも両者の体の形の違いは何となく分かると思います。
このブリ・ヒラマサはどちらも90cm台の個体ですが、ブリの方は11キロ後半で12キロに迫る重量。
一方でヒラマサは7キロクラスにとどまっていて、体の厚みによって重さに違いがあります。
小型の個体・やせた個体も存在する
特にブリは幼魚を含め、コンディションの差が大きく出やすい傾向があります。
水深が浅くて暖かい場所にいるブリだったり、小型の個体は痩せやすい印象です。
ですので、場合によっては上で紹介した個体ほどはっきりした体型の違いは無いことも多いですね。
口の形の違い
次は、ブリのヒラマサ口の違いについて見ていきましょう。
口の角・カンヌキを見る
ブリとヒラマサは口の角・カンヌキと呼ばれる場所の形に差があります。
ブリはカンヌキが角ばっているのに対し、ヒラマサは丸みを帯びた形状をしています。

これはヒラマサの口の形状で、ピンクで囲ったカンヌキの形が何となく丸っこい。

一方のブリの口の角の形は直線的な形状をしており、ヒラマサほど丸くないです。
ただし、ブリのカンヌキの形状も完全な角ではないので、多少の丸みはありますね。
ブリとヒラマサの顔つき
ブリとヒラマサは顔つきが微妙に違います。

ブリ(上)の方が口先が尖っており、目までの距離が遠くてシュッとした感じです。
一方、ヒラマサ(下)の方は丸みを帯びた顔つきをしています。
見慣れてくると、この顔のバランスを見ただけでもだいたい判別がつくようになってきますね。
ヒレと黄色いラインの重なり具合が違う
ブリとヒラマサには体に黄色いラインが走っています。
このラインとヒレの位置関係に若干の差があり、この差は魚種を見分けるうえでかなり有力で、パッと見で分かりやすいですね。

この個体はブリ。少し見にくいかもしれないですが、黄色いラインの位置がヒレよりも背中側にあります。
生きている時はヒレの動き方によって多少変わりますが、ブリの場合は黄色いラインとヒレが交差しない~若干触れるくらいの位置関係になるのが基本です。
一方でヒラマサの場合は

こんな感じで、ヒレと黄色いラインがしっかりと交わっている個体が非常に多くなります。
ヒレと黄色いラインの交わり方は分かりやすい見分けのポイントになり、見分ける際の優先度としてはかなり高くなりますね!
腹びれ・尾びれの形の違い
次は腹びれと尾びれの形の違いについて紹介していきましょう。
腹びれが大きくて黄色いのがヒラマサ
ブリとヒラマサを比較してみると、腹びれの大きさと色が少し違います。
個体差がある程度存在するものの、ヒラマサの方が腹びれが大きくて黄色っぽい傾向です。

これはヒラマサの腹びれ。かなり黄色みが強く、胸びれよりも腹びれの方が大きい位ですね。
一方でブリの場合は、腹びれがヒラマサよりも白っぽくて小さいです。
ただし、ブリの場合も小型の個体や生きている個体はヒレが黄色っぽいものもいます。
ですので、腹びれを重点的にチェックして見分けることはないですね。
尾びれの形と大きさ
今回ちょうど同じくらいの長さのブリとヒラマサが入ったので、ちょうどいい比較画像を撮影できました。

上がブリの尾びれで下がヒラマサ。
両者を比べてみると、同じ長さの個体の場合はヒラマサの方が尾びれの大きさ自体が少し大きいですね。
また、ヒレの形自体にも若干の差があります。
ブリの方がヒレが直線的な形状で外を向いている感じです。
ヒラマサの方が尾が大きく弧を描いたような形状をしており、より大きく・強く水を動かすようになっているんでしょうか。
ヒレの形違いに関しては、経験を積めばパッと見で何となく分かるくらいの差は存在していますね。
ブリとヒラマサの大きさ(重さ)
ブリとヒラマサは成長すると大きさ(重さ)にかなりの違いがあります。
ブリは大きくても10kg台
ブリは大きくなると1m程度は超えてきますが、大きい個体でも15kg~18kgくらいです。
ブリの場合は10kgを超えればまずまず良型で、12kg・13kg程度になれば十分大きい分類です。
魚屋にいても14kgや15kgといった大型のブリは中々入荷せず、12kg台程度までが大半を占めています。
ブリの場合は1m前後になるとあまり長さは変わらず、コンディションによる重さの差が非常に大きくなってくる傾向がありますね!
ヒラマサは20kg以上に成長
一方でヒラマサの場合は10kg台というのは超大型というわけではなく、20kg・30kg・それ以上まで成長します。
ブリよりも大きく成長する魚で、長さでいうと2m以上の個体も存在しています。
ブリとヒラマサの味・身質の違い
ブリとヒラマサは実際に捌いてみると身質にかなり大きな違いがあり、味わいも当然変わってきます。

実際にブリとヒラマサを捌いてみると、こんな感じです。
ブリ(上)の方がピンク色が濃い身質をしていて、ヒラマサ(下)の場合はどちらかというとタイやカンパチのような白身系ですね。

捌いて刺身に切るとこんな感じ。
ちなみに上がブリ・下はヒラマサです。
このブリは脂が非常に良く乗っていて上質な為、色に関して言えば両方ともかなり白っぽくなっています。
濃厚な味・脂が特徴のブリ
ブリはカンパチやヒラマサと比較すると、濃厚で味のある身が特徴になります。

これは私が今まで捌いてきた中でも最上級の脂の乗りの天然ブリです。
こうなってくると、魚の身というよりも肉といった感じで、切っただけで脂がジュワジュワと出てきますね!

非常に良質なブリを刺身に切ってみるとこんな具合になります。
見た目的にも、脂が非常に良く乗っているのが明らかですよね!
味わいとしては、ブリの方がしっかりとした旨味があって独特な風味があります。
また、ブリは血合いが多く、他の魚種よりも身が劣化しやすい性質もありますね。
アタリの個体を引けばこのような絶品ぶりが手に入ることもありますが、天然ブリの場合は個体による当たり外れがかなり大きいです。
見た目的には肥えていても、脂が乗っていない個体もいるから難しい魚だったりします。
美味しいイメージがある日本海の寒ブリであっても、すべての個体が脂ノリノリというわけではありません。
外れを引くと、脂はかなり薄いですからね。
▼脂の乗ったブリの見分け方の詳しい解説は【ブリの鮮度・脂の乗った個体の見分け方徹底解説】を参考にどうぞ。
魚屋の見分け方を詳しく解説します。
身が強く・すっきりしたヒラマサ
ヒラマサの場合は、ブリと比較すると脂が乗っていなくてもパサパサになりにくく、当たり外れが少なくて風味も癖があまりない淡白な傾向があります。
大型のヒラマサになると脂が乗る個体もいますが、ブリほど濃厚な味わいではありません。
身質としてはブリよりも水分・血合いが少なくて「白身魚に近くて食べやすい青物」という感じでしょうか。

ヒラマサの身の断面はこんな感じで、血合いが非常に少なくて身が引き締まっています。

ブリと同じく刺身にするとこんな感じで、一般的にはブリと比較するとすっきりした身質をしています。
ただしヒラマサの場合も10kg以上の大型になってくると、もう少し脂はのってきます。
養殖魚も存在
ブリやヒラマサは天然物のほかに養殖の個体も流通しています。
養殖の個体の場合は全体的に脂が乗りますが、やはりブリの方が脂は濃くて濃厚な味がしますね。
ヒラマサも養殖の個体はかなり脂は乗りますが、ブリと比較すればすっきりした味わいになっています。
ブリとヒラマサの生息場所・引きの違い
釣り好きの方向けになりますが、ブリとヒラマサは似ているようで釣れる場所に違いがあります。
ヒラマサは根や海底の変化に着く習性を持つ
ヒラマサは開けた場所に多く生息するというより、海底に根や駆け上がりに対してピタッと着く習性がブリよりも強いですね。
特に浅場の根がきつく・潮がガンガン効くような場所は、ブリよりもヒラマサが狙いやすい地域もあります。
一方でブリの場合は海底の変化に着く習性もありますが、開けたポイントにも回遊しやすいですね。
生息数は地域によってかなり差があるようで、私の出身地である静岡の場合はヒラマサを狙って釣るのはかなり難しく、メインはブリになります。(幼魚含む)
引きの強さは全く違う
同じ重さのブリとヒラマサを比較すると、ヒラマサの方がブリよりも強く引いて激しいファイトをします。
私が初めてヒラマサを釣った時は、何が掛かったのか分からないくらい引いたのを覚えていますね。
体感的には、同じ重さだったらヒラマサの方が強く・スピーディーに引く感じですね。
ブリはヒットすると横方向に走ったり、重たい引きのイメージがあります。
また、ヒラマサやカンパチはヒットすると、根に入ろうと下に突っ込む引きがかなり強いです。
カンパチとヒラマサを比較すると、引き込みにパワーがあって激しいのがカンパチ。
ヒラマサの方がパワーの面では若干劣るものの、その分猛スピードで長い距離を疾走するような印象ですね。
おすすめ関連記事!
▼魚の鮮度の見分けを徹底解説!
▼ブリの美味しい個体の見分け方を解説
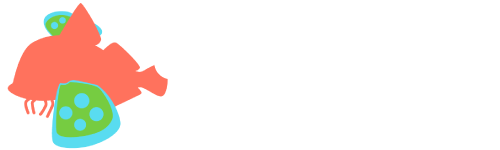





こんばんは
ヒラマサ、ブリの違いはある程度把握してましたがここまで徹底解説してるサイトはまるなかさんの所だけですね、大変勉強になりました
千葉だとヒラマサがサーフでもたまに釣れるので1番狙ってる魚です
あのヒキは病み付きになります
新環境になられるそうで大変だとは思いますが応援しています
私は頑張っても月10回程の釣行しか行けませんが少しづつ積み重ねて行こうと思います
お互い頑張りましょう
こんにちは、まるなかです。
静岡ではヒラマサは殆ど釣れないので、釣れる地域がうらやましいですね!
今は寒くて釣り場調査が困難なので、もう少し暖かくなったら新天地へ行こうと考えています。
今後ともよろしくどうぞ(#^^#)