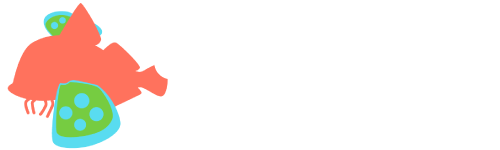こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。
さてさて、今回はハゼ釣り講座をやっていきましょう。
今日のテーマは、ハゼが釣れるポイント・場所探しの基本やコツについて紹介していきます。
ネットで情報を見ればハゼ釣りポイントはある程度分かることも多いですが、良く釣れるポイントを絞り込んだり、誰も知らない良く釣れるスポットを見つけるためには、自力で探すスキルが重要になってきます。
今回は、普段毎日のように釣りをして生活している私の実釣経験を基に、ハゼ釣りポイントを探す際に意識していることを掘り下げて解説していくので、参考にしてもらえたら嬉しく思います。
✔管理人の経験・実績
私の経験・実績としては
- 釣りのために仕事を辞めて移住、現在は魚釣りで生計を立てています
- 年間釣行数300以上(現在はほぼ365日釣行)
- 渓流釣りやタナゴ釣り~ヒラマサ釣りまで、ジャンル問わず様々な釣りができます
- メーカーからプロスタッフとしての勧誘あり
- メーカーの商品開発時に私のタックルインプレッションを活用
こんな感じでほぼ毎日釣行を重ねて釣りを中心に生活していて、実釣実績も残しています。
釣果実績については釣行記やTwitterを見てもらえれば、ほぼ毎日様々な魚を釣っていることが分かると思います(一番更新頻度が高いのはTwitter)。
ハゼ釣りポイント・釣れる場所探しの基本と要点

まずは、ハゼが釣れやすいポイントの特徴・要点についてまとめておきます。
これらの条件が複合してくる釣り場になってくると、ハゼが釣れる可能性はかなり高くなってくるはずです。
- 主な釣り場:河川の下流・河口域や水深が浅い穏やかな内湾の奥まった場所など
- 塩分濃度:汽水域など、低い塩分濃度を好む
- 流れの強さ:流れが緩い場所
- 底質:砂底・泥底を好む。斜面や硬いものが絡んでくる場所がベスト
- 水深:浅い分には問題ない。3mくらいまでの場所を狙うことが多い
- 時期:季節によって釣れやすい場所は変化する。ハゼは春・初夏にかけて汽水域を遡上。晩秋・初冬にかけて海へ落ちる
私がハゼ釣りポイントを開拓する時は、これらを意識することが多いですね。
ハゼが好むポイント・釣り場の条件
塩分濃度
ハゼ(マハゼ)は塩分濃度があまり高くない場所を好む魚です。
ですので、河川や放水路などが流れ込んでいる場所だったり、内湾の汽水域がポイントになるわけですね。
一方、外洋に面している塩分濃度が高いサーフや磯で狙って釣るのは非常に難しい魚になります。
ハゼが釣れるポイントでは
- ウナギ
- テナガエビ
- スズキ(マルスズキ)
- クロダイ
- キビレ
このような魚が生息していることが非常に多いです。

ですので、これらの魚のポイントとして有名な釣り場であれば、ハゼが釣れる可能性も比較的高くなりますね!
流れの強さ
ハゼは底付近に張り付いていたり、ピョンピョンと底を跳ねるように移動する魚です。
常に泳ぎ続けているのは苦手なので、基本的には流れが緩い場所を好みます。
条件が揃っていても流れがガンガン利く場所ではあまり釣れず、ほとんど流れがない~緩やかに流れが利いている場所に集まります。
底質
ハゼが好む底質としては、砂底または泥底のポイントになります。
ただし、一面が開けた砂・泥底のポイントよりも、ハゼの隠れ家となる障害物が混じっている場所の方が魚影は濃くなりやすいです。
メインは砂泥底ですが、時々軽く仕掛けが引っ掛かるような場所の方がハゼ釣りポイントとしては有望になりますね。
特に大型のハゼは障害物の際にピッタリとつき、縄張りを持っていることも良くあります。
水深
ハゼは水深が浅い場所の方が釣れやすい傾向があります。
岸からハゼを狙う場合、私の場合は深くてもだいたい3mくらいまでの場所を狙うことが多いですね。
一方、浅い分には問題なく、潮周りなどにもよりますが、釣れる時は水深がヒザ下くらいのポイントでも全く問題ありません。
ただし、水深が非常に浅い場所は釣れる時と釣れない時の差が大きく、潮の満ち引きによる潮位変化などの影響を受けやすく、釣果ムラが出やすい傾向を感じます。
安定して釣るのであれば、水深は1m~2mくらいの場所が比較的無難な印象ですね。
ハゼ釣りが楽しめる代表的なポイント
ハゼが釣れる可能性が高いポイント・釣り場の代表的なものを紹介していきます。
河川の下流・河口周辺

川の下流~河口周辺は汽水域といい、海水と淡水が混ざり合う場所になりますね。
ハゼは塩分濃度が低い状態の場所を好む傾向が強く、ハゼ釣りでは川の河口周辺はベストポイントと言ってもいいくらいですね!
規模の大きい1級河川のような川でもハゼは釣れますし、川幅が数メートルしかないような小さな水路のような場所でもハゼは十分狙えます。

流れが早い場所よりも、都市型河川と呼ばれるような、流れが平坦でゆったりした場所の方がハゼの魚影が濃い事も多いです。
ハゼは身近な場所を流れいている、ちょっとした川がハゼ釣りでは良いポイントになることも非常に多いです。
秋に延べ竿を使って釣りをしている方を見かけた時は、ハゼ釣り師の可能性が大ですね!
河口や排水溝周辺の港湾部

ハゼは川の下流で釣る印象が強いですが、川が流れ込んでいる場所の近くの海側であっても、狙ってみると結構釣れるもの。
ただし、海はハゼ以外の外道が多く釣れる事も多くなりやすいです。
キスやメゴチ、小型のカサゴなどと合わせて狙うような五目釣りになりやすい印象です。
遠浅な地形の湾奥
海岸線が複雑な形をしているリアス式海岸の奥まった場所や、汽水湖の遠浅なエリアも、ハゼが釣れる可能性が非常に高いですね。

こんな感じの波が穏やかで流れも緩く、水深が浅くなっている汽水域の奥まった場所は、ハゼが大好きなポイントになります。
人工的に作られた運河や埋立地

地域によっては、人工的に作られた運河や埋立地などがあると思います。
このような場所は、水深が全体的に浅くてハゼが生息するのに適している場所が多いです。
釣果アップのためのポイント選びのコツ
水深が浅い場所もしっかり狙う
特に上げ潮・満潮周りの時間帯にハゼを狙う時は、水深が非常に浅い場所も忘れずにチェックしておきます。
ポイントによっては、水深が15cm・20cm位しかないような超シャローエリアにもハゼは差してきます。
水深が非常に浅い場所にやってきたハゼ達は餌を求めている高活性な個体であることも多く、餌を入れると入れ食いになることも良くあります。

このポイントは満潮になると沈む護岸があり、水深は20cm位しかありません。
しかし、潮位が上がると深い場所からハゼが上がってきて良く釣れるんですよね。
こういうちょっとした場所を逃さず狙えるようになると、取りこぼしていた魚も拾うことができるようになりますね。
かけあがりを正確に把握する
かけあがりというのは、水中にできた斜面・段差のことですね。
かけあがりの存在やその位置は魚釣りにおいては超重要で、魚はかけあがりを基準にして行動することが非常に多いんですね。
かけあがりの斜面自体が魚が潜むポイントになりますし、潮位が変化した際にかけあがりの斜面を基準にして浅い方へ動いたり、逆に深い場所に落ちたり・・・。
はじめて釣行する釣り場では、水深が変化するかけあがりの位置やその角度などを把握する癖をつけておくと良いですよ!
カキガラ・捨て石などの硬いものは一級スポット

ハゼは砂泥底を好む魚ですが、そこにカキガラや沈み岩・テトラなど、硬いものが点在しているスポットは1級エリアになりやすいですね。
実際に私がハゼ釣りポイントを探す時は、仕掛け(オモリ)を投げて底をズルズルと引き、沈んでいる障害物の有無やその位置を正確に把握するようにしています。
ハゼに限ったことではありませんが、魚達は何もない開けたポイントより、隠れ家や餌となる小動物の住みかとなる障害物がある場所を好みます。
岸沿いも忘れずに探る
特に護岸や石積の河川・岸壁などで釣りをする時は、まずは足元から釣りをしていくのが重要になります。

石積エリアは見た目のままで、足元の沈んだ石にハゼが良く着きます。
また、護岸・岸壁の場合も同様で、岸際には基礎を作るために捨て石が入っていることが良くあり、その周辺にハゼが良く着きますね。
垂直な護岸・岸壁が影になることで障害物の役割も果たしますし、足元付近はハゼ釣りにおける1級ポイント。
ついつい沖の方に目がいきがちかもしれませんが、足元から順に狙っていく癖を付けましょう。
ちょっとした流れ込み
ハゼは流れの緩やかな場所を好みますが、全く流れが無い場所よりもある程度水の動きに変化のあるスポットに集まりやすいです。

このようなちょっとした流れの合流などであっても、ハゼ釣りにおいては十分なポイントになります。
場所によっては、地下からの湧水があったりします。
非常に小さな水路や排水の流れ込みであっても、見逃さずに仕掛けを入れてみましょう。
時期に合わせたポイント選び
ハゼは湾内などで産卵し、孵化した稚魚は春~初夏にかけて汽水域へやってきます。
そして季節が進んで晩秋~初冬になると、産卵を意識して海へ下るようなパターンが多いです。
ですので、釣行する時期によって狙うポイントも少しずつ変えていくのがベストです。
私の目安としては、
- 8月頃まで・11月以降:比較的海に近い場所
- 9月~10月くらい:ハゼが釣れる範囲は広い。河川内や塩分濃度がかなり薄い場所まで狙う
こんな感じで、シーズン序盤・終盤は上流域はほとんど狙わず、海に近い場所がメインポイントになります。
一方、ハゼ釣りシーズン真っ盛りとなる9~10月頃は、ハゼがかなり上流の方まで遡上してくるので、河口から離れた場所まで広く狙って魚を探すようにしていますね。
▼ハゼ釣りの時期に関する詳しい解説は【ハゼ釣りの時期・シーズンと時間帯選びの基本を徹底解説】を参考にどうぞ
上流域と下流域
時期によってハゼが釣れやすい場所は変化するわけですが、9月~10月頃のハイシーズンになると、海に近い河口周りよりも河口から離れた上流側のポイントの方が、良型のハゼが揃いやすいことが良くあります。

もちろん年や釣り場によって癖は変化しますが、上流にガンガン差してくるハゼは、型が揃いやすいという場所が多い傾向を感じるんですよね。
一方、河口に近いポイントの方がサイズは伸びにくいものの釣果ムラは出にくく、いつでも安定した釣果が出やすい印象ですね。
まとめ!

今回はハゼ釣りのポイント選びの基本やコツについて紹介しました。
まずは
- 塩分濃度が薄い汽水域
- 流れが緩いところ
- 砂泥底の場所
- 水深が浅め
このような条件が揃っている場所を優先的に狙ってみてください。
最初はよくわからないかもしれませんが、経験を積めば、釣り場の風景を見ただけでハゼが釣れそうかどうかは分かるようになってきます。
後は細かい地形の変化などを見逃さないように、足元から順にハゼが釣れそうなポイントに検討を付けて狙っていきます。
ハゼは底付近に潜む魚なので、地形変化(障害物)の把握が非常に重要です。
仕掛け(オモリ)を引っ張って頭の中で水中の様子をイメージし、ハゼが集まりそうなスポットを絞り込んでいくようにしてくださいね。
今回の解説を参考に、ハゼ釣りのポイント探しの役に立ててもらえたら嬉しく思います。
おすすめ関連記事
▼ハゼ釣りに使う餌の種類と使い分け・使い方のコツを徹底解説!
これからハゼ釣りに挑戦したい初心者の方へ、必要な基礎基本をまるっと解説します