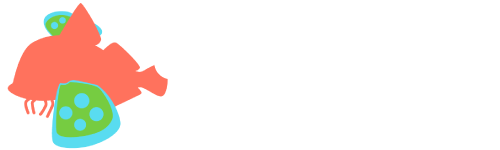こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。
さてさて、今回はちょい投げ講座をやっていきましょう。
今日のテーマは、ちょい投げ釣りに使う餌の種類や使い分けの基本・コツなどについて、少し掘り下げて紹介していきます。
狙う魚の種類や状況により、使いやすい餌の種類や使い方は少しずつ変わってきます。
この機会に基本となる考え方を覚え、実釣時の参考にしてもらえたら嬉しく思います。
✔管理人の経験・実績
私の経験・実績としては
- 釣りのために仕事を辞めて移住、現在は魚釣りで生計を立てています
- 年間釣行数300以上(現在はほぼ365日釣行)
- 渓流釣りやタナゴ釣り~ヒラマサ釣りまで、ジャンル問わず様々な釣りができます
- メーカーからプロスタッフとしての勧誘あり
- メーカーの商品開発時に私のタックルインプレッションを活用
こんな感じでほぼ毎日釣行を重ねて釣りを中心に生活していて、実釣実績も残しています。
釣果実績については釣行記やTwitterを見てもらえれば、ほぼ毎日様々な魚を釣っていることが分かると思います(一番更新頻度が高いのはTwitter)。
ちょい投げ釣りでの餌の種類の基本

まずは、ちょい投げ釣りに使われることが多い餌の種類について、ざっくりと紹介していきます。
ちょい投げ釣りに使われる餌をざっくり分類すると、
- 虫餌:赤・青イソメなど
- サバ・イカなどの身餌
- アサリなどのむき身
- 人工イソメ・ワーム
この4つに分類できます。
これらの餌を状況によって使い分けていくのが基本になりますが、とりあえずは赤イソメまたは青イソメを使っておけば、だいたい何とかなります。
初心者の方は、イソメを使ってちょい投げ釣りに挑戦するのがおすすめ!
赤イソメ
赤イソメの特徴・釣れる魚

イソメには種類がありますが、赤イソメ(石ゴカイ)は、主にキスやハゼなどの口が小さい魚を狙う時に使いやすい虫餌になります。
細くてやや小さめのイソメなので、虫餌が苦手な方にも比較的使いやすいと思います。
私がキスやハゼを狙う時は、赤イソメを一番良く使いますね。
赤イソメの使い方
赤イソメはそれほど大きくないので、1匹丸ごとつけたり、半分程度にカットして使うのが基本になります。

こんな感じで、餌が針よりも少し長めになるようにセットして使います。
これは私がハゼを釣る時の赤イソメの使い方で、一般的な付け方よりもやや短めに切ってます。
基本的には、アタリが無い時は餌を大きめに。
アタリがあっても針掛かりが悪い時は、餌を小さめに付けるのがおすすめです。
なお、頭の部分を残して使った方が餌持ちが良くなります。
頭の部分をカットした方が食い込みが良くなりますが、餌が取られる確率が少し高くなりますね。
この辺りは状況に合わせ、使い方を微調整してみましょう。
青イソメ
青イソメの特徴・釣れる魚

青イソメは、赤イソメと並んで海釣りの代表的な釣り餌になります。
見た目は似ていますが、赤イソメよりも少し大きめです。
大きさにバリエーションがあるので・細・中・太といった具合でサイズ別に売られていることもあります。
主に中型以上のキスやハゼの他、カレイやカワハギ・セイゴ・チヌ・根魚など、少し口が大きい魚を色々釣りたい時におすすめです。
エサが太くなるので、キスやハゼのサイズが小さい時は、食い込みが少し悪くなります。
また、青イソメは夜釣りなどで使われる機会も多いですね!
サイズ選びの目安としては、
- キス・ハゼ:細め
- カワハギ:細~中
- カレイ・セイゴ・チヌ・根魚など:中~太
だいたいこれくらいが使いやすいと思います。
サイズが選べる場合は、狙うターゲットに合わせた大きさのものを買うようにしましょう。
青イソメの使い方

青イソメの使い方は、基本的には赤イソメと同じような感じで、ある程度のサイズでカットして使います。
キスやハゼ・カワハギなどを狙う際は、餌をカットして使わないと針掛かりが悪くなりやすいですね。

なお、口が大きいセイゴや根魚などを狙う際は、アピール力を出すためにあえて1本丸ごとつけてみたり、複数のイソメを付ける房掛けにすることもあります。
イカ・サバなどの切り身
特徴・釣れる魚

イカやサバを細長くカットした切り身餌ですが、基本的には根魚狙いで使われることが多いですね。
大きさを自由に決めて作ることができ、口が大きい魚に対して、しっかりとボリュームのある餌を作ることができます。
イカやサバなどの身餌は、虫エサなどと比較して餌持ちが非常に良く、小さな外道が多くて厄介な状況下で強い効果を発揮します。
特に、夜釣りなどで使うことが多いですね。
身餌の使い方

身餌の使い方ですが、身が厚いと針先が身の中に埋まってしまうので、針掛かりが悪くなりやすいです。
また、餌が硬くなって海中での動きが悪くなってしまいがち。
ですので、身が厚く残っている時は、ハサミやナイフなどで身を薄く削いで使うのがおすすめです。
皮目に少し身が残っていれば十分魚は釣れますからね。
なお、川が残っていないと餌持ちが非常に悪くなるので、皮が非常に重要になります。
餌持ちが悪い時は、あらかじめ塩を振って水分を抜き、身を締めて使うと良いです。
アサリのむき身

アサリ餌は、カワハギ釣りの特餌になります。
カワハギ以外では、フグやベラなどが非常に好反応を示します。
胴付き仕掛けを使う際によく使う餌ですが、天秤を使った仕掛けでも問題なく使えます(強く投げると餌が落ちやすいので、軽めに投入します)。
アサリの使い方としては、水管に針を1度差して抜き、次にベロの部分に2回ほど針を縫い刺しにします。
最後にワタの部分に針を刺し、針先を出せばOKです。
なお、アサリもそのままだと餌持ちが悪いことがあるので、その場合は塩を振って水分を抜くと良いです(カワハギ釣り用のアサリを締めるための商品もあり)。
人工イソメ・ワーム(ガルプ・パワーイソメなど)
人工イソメ・ワームの特徴と釣れる魚

最近はイソメに似せた人工イソメ(ワーム)も釣具店で売られています。
集魚成分が入っていて、強烈な味と匂いで魚を引き寄せることが可能になっていますね。
人工イソメ・ワームで釣れやすい魚としては、
- キス
- ハゼ
- セイゴ
- チヌ
- 根魚
主にこのような魚が狙えます。
お手軽に使うことができますし、虫エサが苦手な方にもおすすめです。
注意点としては、食いが良い時は普通にアタリが出て魚が釣れますが、食い渋りに弱いこと。
根魚の場合は、本物の餌と大差なく釣れることが比較的多いんですが、キスやハゼなどは、食い渋ると本物の餌にアタリが集中したり、アタリが出ても針掛かりしなくなることがあります。

人工イソメは好きな時に使えて非常に便利な餌ですが、やはり本物のイソメには敵わないことも多いです。
ですので、確実に釣果を出したいのであれば、やはり赤イソメや青イソメを使うことをおすすめしますね。
人工イソメ・ワームの使い方
使い方に関しては、イソメと全く変わりません。
口が大きい魚を狙う時は丸ごとつけることもありますが、基本的には何等分かにカットして使用します。
ちょい投げ釣りの餌に関するよくある質問
餌は何種類持っていくか?
ちょい投げ釣りに使う餌の種類は色々ありますが、沢山持っていくと手間になりますし、実際には使わない餌も出てくると思います。
私の場合、餌の種類は持って行っても2種類くらいまでにしています。
キスやハゼを狙うのであれば、赤イソメのみ。
もしくは、赤イソメと青イソメを半分ずつくらい用意していくことが多いですね。
餌を交換するタイミング
餌を適切に交換するのは非常に重要で、状況によっては餌の鮮度でアタリの数が何倍も変わったりします。
特にキス釣りでは、餌の状態で魚の反応が大きく変わりやすい印象があります。
面倒くさがらず、活きのいい新しい餌をどんどん使うようにしてください。
イソメが魚に噛まれてボロボロになったり、体液が出てしまってビヨーンと伸び切ったような状態になったら、交換の合図です。
切り身餌などの場合も同様で、ボロボロになってしまったら新しいものに取り換えましょう。
基本的には新しい餌の方が集魚力が高くてアタリが良く出ますが、近距離戦でハゼを狙うような時は、あえてボロボロになった使い古しのイソメを使うこともあります。

ボロボロになって伸びたようなイソメは魚の吸い込みが良く、針掛かりが安定するからです。
しかし、集魚力は低くなるので、目の前に魚が居ることが分かっている状況下において、積極的に誘いを掛けて使う機会が多いですね。
まとめ!
今回はちょい投げ釣りに使う餌について、少し詳しく解説しました。
- 大きく分けると、虫餌・身餌・アサリのむき身・人工イソメ(ワーム)に分類できる
- イソメ餌が無難に使いやすく、様々な魚が狙える
- 赤イソメは小さく、キスやハゼ釣りに。青イソメは五目釣りにおすすめ
- 身餌は根魚狙いなどに使うことが多く、外道に強い
- アサリはカワハギ釣り用の餌
- 人工イソメ・ワームは、便利で使いやすいが、食いが悪いと本物の餌には敵わない
要点をまとめると、こんな感じですね。
基本としては、赤イソメまたは青イソメを使うのがおすすめですね。
イソメを使っておけば、キスやハゼといったちょい投げ釣りの定番ターゲットを広く狙うことができますよ!
今回の解説を参考にしてもらえたら嬉しく思います。
おすすめ関連記事