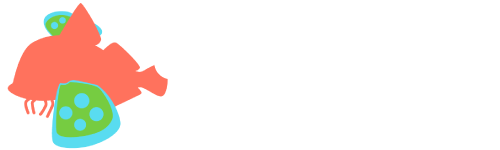こんにちは、まるなか(@marunakafish)です。
さてさて、今回はうなぎ釣り講座をやっていきましょう。
今日のテーマは、うなぎが釣れる時期や時間帯選びのコツについて、少し詳しく解説していきます。
うなぎは1年中同じように釣れることは無く、釣行する時期によって釣果は変わります。
また、うなぎは時間帯によってかなり活性が変化する魚なので、釣行するタイミングも超重要。
釣れる時はアタリが連発することも良くありますが、時合いを過ぎるとパタッとアタリが無くなって全く釣れなくなったり・・・。
今回は毎日釣りをして生活している管理人の実釣経験を基に解説していくので、うなぎ釣りに挑戦する際の参考にしてもらえたら嬉しく思います。
✔管理人の経験・実績
私の経験・実績としては
- 釣りのために仕事を辞めて移住、現在は魚釣りで生計を立てています
- 年間釣行数300以上(現在はほぼ365日釣行)
- 渓流釣りやタナゴ釣り~ヒラマサ釣りまで、ジャンル問わず様々な釣りができます
- メーカーからプロスタッフとしての勧誘あり
- メーカーの商品開発時に私のタックルインプレッションを活用
こんな感じでほぼ毎日釣行を重ねて釣りを中心に生活していて、実釣実績も残しています。
釣果実績については釣行記やTwitterを見てもらえれば、ほぼ毎日様々な魚を釣っていることが分かると思います(一番更新頻度が高いのはTwitter)。
うなぎが釣れる時期・ベストシーズン
5月~10月頃がおすすめ
うなぎ釣りの時期ですが、基本的には水温が高い時の方がうなぎの活動が活発になりやすく、釣果は出しやすい傾向にあります。
1つの目安としては、だいたい5月~10月くらいまでがうなぎ釣りのシーズンですね。
真冬でも全く釣れないことはありませんが、一発大物狙い向きの時期になり、初心者の方にはおすすめできません。
ベストシーズン

うなぎが一番釣りやすくなる時期の傾向としては、私の経験ではだいたい6月の梅雨入り前後~8月くらいまでですね。
その中でも、湿度が高くてジメジメしている6月中旬~7月下旬くらいまでの梅雨時期は、雨による濁りや増水により、うなぎの活動が特に活発化しやすい印象があります。
私の場合、うなぎ釣りに行く頻度が最も高くなるのは6月~7月いっぱいくらいまでですね。
うなぎ釣りのルール
禁漁期間
うなぎは河川によって漁業権が設定されていたり、地域の条例で採捕可能な時期が決まっていることがあります。
違反して釣りをすることは罰則の対象になるので、釣行する際はあらかじめルールを確認しておくこと。
ちなみに、私の地元静岡県の場合は10月~2月は全河川で禁漁になっています。
この期間は漁業権の有無に限らずうなぎは禁漁なので、釣りをすることはできません。
遊漁券の必要性
漁業権が設定されている場所で釣りをする場合は、あらかじめ遊漁券を購入する必要があることも多いです。
渓流魚やアユと同様、うなぎ釣りには遊漁券を購入しておかないと釣りができないフィールドもあるので、特に初心者の方は適当に釣行しないようにします。
遊漁券が必要な場所では、遊漁券無しの釣行は密漁扱いになります。
うなぎ釣りの時期・シーズンの流れ
春
うなぎは水温が低くなると、底や岩の隙間などに入ってしまって餌をとらなくなることが多く、低水温期は基本的にオフシーズンになります。
4月くらいまでは水温が低くて餌となる小魚やエビなどの活動も活発ではなく、うなぎを釣る難易度は高い傾向があります。

だいたい5月くらいになり、陸上の気温がグングン上がってくると水温も上昇し、うなぎの活動が活発になってきます。
しかし、春は冷たい雨が降ると水温が低くなり、うなぎの活性が落ちて釣りにくくなることもあります。
暖かい雨の後や、何日か天気が続いて水温が上がった時に釣行するのがおすすめですね。
夏
夏は水温が上昇し、うなぎの活動も活発なシーズンになります。
特に蒸し暑くてジメジメしているマズメ~夜間は、うなぎの活動が活発になりやすく、巣穴から離れて餌を積極的に探し回る個体が増えやすい印象を持っています。
夕立や低気圧の通過で少しまとまった雨が降り、濁り+増水が絡んだ時は、うなぎ釣行のタイミングとしてはベストですね!
夏に雨が降って良い具合にい河川が濁って増水していると、うなぎ釣りに行きたくてうずうずしてきます。
夏の良い日に当たると、仕掛けを入れた瞬間にうなぎのアタリが連発することもあり、うなぎ釣りが非常に楽しい時期です。
秋
秋といっても、9月頃まではまだ水温が高く、夏からのうなぎ釣りシーズンが継続します。
だいたい10月くらいになると水温が低下し始めて徐々にうなぎの活性が落ちてきて、11月頃になると夏のような数釣りはかなり難しくなることが多いです。
また、河川や地域によってはうなぎの禁漁期に入ることもあるので、場所によってはうなぎ釣り自体ができなくなります。
うなぎ釣り=夏という印象がある方も多いですが、秋のうなぎは脂の乗り具合が非常に良く、夏よりもおいしいことも良くありますね!
冬
冬にうなぎ釣りを楽しむ方はほとんど居ないのが現状だと思います。
しかし、冬でもうなぎは全く釣れないわけではなく、数釣りはできないものの、単発で大型が釣れる可能性があります。
河川内は冬になると水温が一気に低下しやすいので、冬は河川の下流部や海水域を狙うのがおすすめ。
うなぎ自体は河川の河口がある水深があまり深くない湾内にも生息しているので、冬は海にいるうなぎを他の魚も含めた五目釣りで狙うと楽しいですね!
うなぎの旬・脂の乗り
うなぎは夏場に食べる機会が多い魚ですが、食べておいしい時期としては秋~初冬にかけてですね。
一般的に出回っている養殖のうなぎは1年中そこそこ脂がありますが、釣れる天然うなぎは時期によって身質が変化しやすいです。
基本的には、水温が徐々に下がり出してくると、うなぎは体に栄養を蓄えるので脂が良く乗ります。
だいたい10月~12月くらいのうなぎは良く肥えていて身が厚く、脂が乗っていて美味しい個体の割合が多い印象ですね。
美味しいうなぎを釣るのであれば、ベストシーズンの夏よりも少し後のタイミングがおすすめ。
うなぎ釣りの時間帯
うなぎ釣りは釣行する時間も非常に重要で、急にバタバタとアタリが出たと思ったら全く釣れなくなったり。
明確な時合いが存在することも多く、釣果に大きく影響しますね。
朝・夕マズメ
うなぎが釣りやすい時間帯としては、朝・夕マズメですね。
日の出前の暗い時間・日没後の真っ暗になる直前~直後くらいのタイミングは、比較的うなぎの活性が上がる確率が高く、釣果実績としても高いですね。

私の場合、朝マズメの釣行するのは体力的にも結構しんどいので、夕マズメからの釣行がメインです。
日が傾いてきた頃の時間にポイントへ入り、薄暗くなってきたら餌を付けて仕掛けの投入を始めるような感じ。
真っ暗になるかならないかくらいのタイミングから、夕方のチャンスタイムに入るパターンが多いですね。
日中
日中のうなぎ釣りですが、釣り方やポイントを選べば釣果を出すことは可能です。
しかし、マズメや夜間のように適当に仕掛けを投げて釣れることはほとんどありません。
日中にうなぎを釣る場合は
- 大雨の後のかなり強い濁りが入った時
- テトラや岩の隙間などをダイレクトに狙う
このような条件・釣り方がキーになります。
強い濁りが入っていると、うなぎは日が昇った時間でも動きが活発になりやすく、釣果が出る可能性は高くなります。
また、日中の巣穴に入っているうなぎを木の棒の先に餌を付けたような仕掛けを使い、穴釣りでダイレクトに狙うのもおすすめですね。
夜

夜間はマズメと並ぶうなぎ釣りにおすすめな時間帯ですね。
日の出・日没が絡むマズメの時間ほどの爆発力は無いことが多いですが、釣果を出せる可能性としては十分です。
場所によって釣れやすい時間帯は違いがあることも多いですが、私の中では日没後~深夜10時くらいまで。
深夜3時くらい~日の出前の薄ぐらい時間帯。
このくらいの時刻が、夜間の中でも比較的実績が高いです。
その他のうなぎ釣りの時期・時間に関する豆知識
潮周りと時間
うなぎは河川の上流域や中流域でも釣れますが、河口周りの汽水域がポイントになることも多いです。
海水の影響を受けるエリアで釣りをする場合は、潮周り(潮位変化)によってうなぎの活性も変化します。
ですので、マズメや夜間といった時間帯だけではなく、潮の満ち引きに合わせて釣行する時間を調整するのが釣果アップにつながります
私の場合は
- 満潮周りの潮位が高い時間は釣れる場所が広くなって無難に釣れやすい
- 干潮周りは周囲より深く掘れている場所などを狙う
- 流れが緩い河川の場合は、流れが程よく出る潮位変動が大きい時間に釣行する
基本的にはこんな感じで考えていますね。
うなぎは完全に流れが止まってしまうと釣れなくなることが良くあるので、流れがほとんど無い河川の下流・河口周りを狙うような時は、潮の満ち引きで流れが出る時間に釣行するのがおすすめですよ!
時合いが何度かやってくる
うなぎの行動パターンは奥が深いものがあり、明らかに活性が上がる時合いが何度かに分かれてやってくる可能性が結構高いですね。

時合いの時間はその時によって変わりますが、基本的には10分~20分くらいのことが多いですね。
時合いになると、複数出していた竿にどんどんアタリが出たり、さっきまで全く気配が無かったのに急に連続で釣れたりするのがうなぎ釣りです。
群れが来るのか、時間が来ると巣穴に潜んでいたうなぎが急に活動を始めるのか分かりませんが、うなぎ釣りには分かりやすい地合いに遭遇することも良くあります。
濁りや悪天候は好条件!
うなぎは濁りがかなり好きな魚で、大雨が降ったりして水の透明度が下がると、明らかに活性が上がります。

泥濁りのような状態でも問題なくうなぎは釣れることが多く、昼や朝・夕でも活動が活発になりやすいですね。
また、夜間でも水が澄んでいる時よりも濁っている時の方が明らかに釣れやすいので、水が濁った時は大チャンスと考えています。
濁っている時は時合いの時間が長くなったり、餌を入れればうなぎがひたすらアタリ続けるようなこともありますよ!
その他にも、濁りが強くなるとハゼなどの厄介な外道のアタリが減るので、ミミズやイソメなどの餌が取られやすい虫エサ類が使いやすくなるのも濁りのメリットです。
まとめ!
今回はうなぎ釣りに関する時期・時間帯選びについて基本やちょっとした知識を紹介しました。
- 基本的には暖かい時期の方が釣りやすい。6月~8月くらいが釣果ムラが少ないベストシーズン
- 天然うなぎの旬は秋~初冬。水温低下で数は釣れにくくなるが、脂が乗った肉厚なうなぎが釣れやすい
- 基本的には夜間を中心に朝・夕マズメ絡みの時間に釣行するのがおすすめ
- うなぎは釣れる時合いが明確に存在することも多い魚
- 短い地合いが何度かに分かれてやってくるような釣れ方をすることが多い
- 濁りはうなぎの活性を上げる大チャンス。濁った日は日のある時間でも釣れやすく、夜間でもプラスに働く
要点をまとめるとこんな感じですね。
うなぎ釣り自体はシンプルで誰にでも楽しめますが、釣行する時期や時間・コンディションによって釣果は大きく変わります。
今回の解説を参考に、釣果アップの役に立ててもらえたら嬉しく思います。
おすすめ関連記事